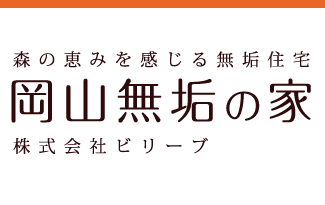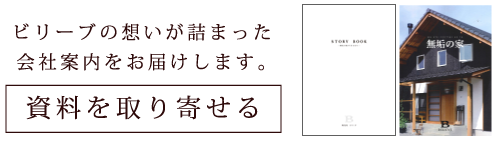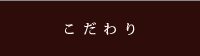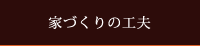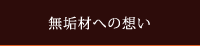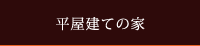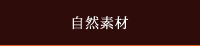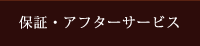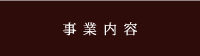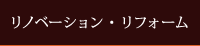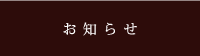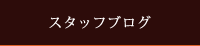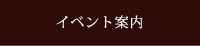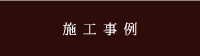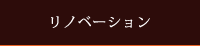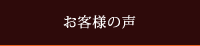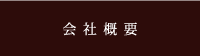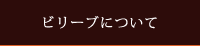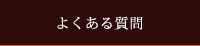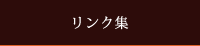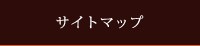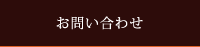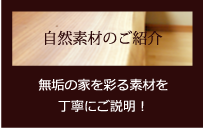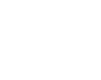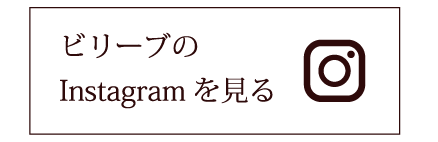意匠部 永瀬です。なにやらモノ物々しい景色
基礎の型枠です。一般にはこのような「鋼製型枠」を使いますが、意匠性のある壁面や厚い壁面などを
作る際には自由度を考え「木製型枠」を使用することが多いです。
因みに今回も「平屋」なので基礎も広い範囲になります。極普通の総二階の建物に対して同じ床面積
を造ろうとすれば単純に基礎や屋根は倍に、これが平屋の割高の一面です。
話がそれましたが、これからコンクリートが打設され、養生期間を経た後型枠がはずされ基礎工事の完了
です。
手前の四角い型枠は、前回ご紹介しました御影石の束石が乗る部分です。
現場の敷地内に「干し柿」。寒くなってきましたねえ。
意匠部 永瀬です。これなんでしょう?
答えは「玄関の敷居」と「束石」です。
これらも今頃ではあまり見ない物なのかと思います。
両方とも素材は「御影石」。
敷居に関しては造作玄関建具の下に入るのですが、厚みは10cmもあります。ほとんど埋まってしまうのですが・・・
地盤改良工事の時にも触れましたが、石は腐食したり錆びたりしません。
自然素材の中でも非常に強い物。
コンクリートなどより断然長持ちするのです。
素材から家づくりをする僕らにとっては欠かせないアイテムなのです。
意匠部永瀬です。今日は基礎が完成したら全く見えない物シリーズ。
鉄筋です。
無数の鉄筋だらけ。ピッチは20cm、昔の家に比べたら過剰なくらいかも知れませんが。
基礎は鉄筋コンクリート造ですから、鉄筋コンクリートの工事基準で造られます。
単純に言うと鉄筋の量が多く、なおかつコンクリートにちゃんと密着していれば、引っ張る力に対して強いことになります。
これだけで日が暮れてしまうので、細かくはまた機会があればご説明します。
建物にとって非常に重要な箇所である鉄筋にはタイトルどおり検査が入ります。
写真奥に見えるのが検査員の方。図面通りか間違いはないか入念に検査します。
当然ですがこれをパスしないと先に進めませんので・・・・・
これから型枠を組んでコンクリートを打設するわけなんですが、ここでまたこの場でしか見ることのできない物。
鎮め物。土地の神様を鎮め、土地や建物が揺らぐことの無い様祈願した物です。
通常は地鎮祭の時に神主さんからもらい、監督が埋めます。僕個人はお施主さんがしてもいいと思うんですけどね。
記念にもなりますし。
今日あたりは基礎工事の真っ最中。これからも安全に進めたいと思います。