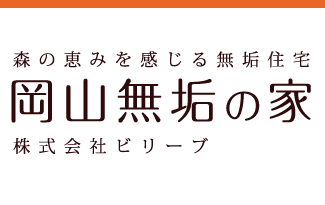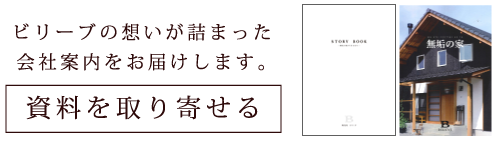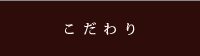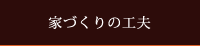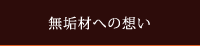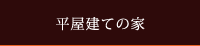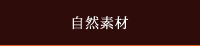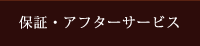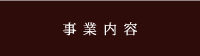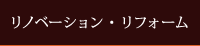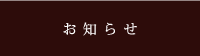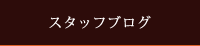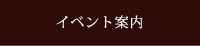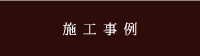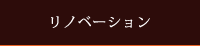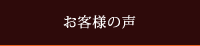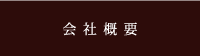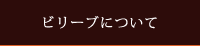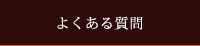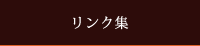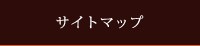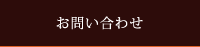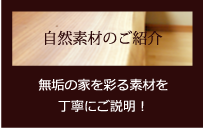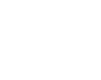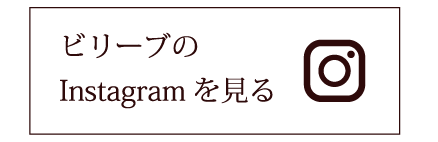さてプランが決定し、住宅設備のショールームにも打ち合わせに行き、金額も決定。次は・・・
行政に対しての図面作成並びに届け出をしなければなりません、要は「確認申請書類の提出」です。
この段階以前にもっとよく調べておかないといけないのが建てようとする土地にまつわる規制。
何故かうちの仕事はこの段階でいつも何かあります・・・(悪い意味ではありませんよ。)
過去にあったのが
建築基準法第43条1項但し書きの申請(道路に関すること)
がけ条例
埋蔵文化財発掘の届け出 などなど・・・
これらは確認申請の前に許可を得ないといけないことです。
今回は埋蔵文化財。岡山のある地域にはこれが適用されるので簡単に言うと地面を掘るときには
この許可が必要になります。
結果的には何も出てこなかったのでほっとしましたが・・・・・
話は戻りますがこれらの許可や申請にはおおよそ1カ月程かかります。もちろん場合によります。
その他今回は「省エネルギー対策等級4」をクリアするための仕様にするなど、別個に書類
が必要になります。
徐々に書類に埋もれていく永瀬でした・・・・
先月無事完成しました「ピクチャーウインドウのある家」。今年は消費税増税などの影響もあり、
建築業界は比較的忙しく、中でも大工さんの手が足らないこともあり、お施主様にはしばし
待っていただくこともありました。
ともあれ年内には完成したのでこちらとしてもほっとしております。
ここでは完成に至るまでを追ってご紹介したいと思います。
施主様との出会いは今年の3月。ご紹介という形でした。
僕らに大事なことは「ヒアリング」、家族構成から年齢、できれば趣味の事まで。プランをしていく
上でどれも重要なことなんです。
聞きにくいことでもありますが、予算の事も。
これらを踏まえて建築スケジュールに沿わせて話を進めていきます。
ビリーブでは「企画住宅」がないので全て一からです。イメージをじわじわ形にしていく
作業を納得いくまで続けます。
ですので図面や書類の枚数は膨大な数になります。基本的に一生住む家ですから出来る限り
時間を掛けるのが良いかと思います。
今回は大きく分けると11回のプラン変更、多分細かいものを含めると20回は超えてるんじゃないかと・・・
ここで言える事は紙の上では変更がききますが、始まったら変更はききにくいと言うことです。
「プランの段階は慎重に」ってことですね。
基本的におうちにいらっしゃる時間の長い奥様にこの段階で頑張っていただくのがベストです。
間取りを載せるのは控えますが、実物を見ていただいてる方はお解りと思いますが、
初期段階の外観はこんな感じでした。
今でもこの形は恰好いいと思っている永瀬であります・・・・
意匠部 永瀬です。今回は「へぇーっ」となるような場面のご紹介。
一瞬何の変哲も無いアルミサッシの写真。のようですが、このサッシは「換気框」付。要は窓をしめたまま
換気が出来るのです。タテに入ったスリットがその部分。
昔は良く見たサッシです。今回採用になった最大の理由は、今の基準法では「24時間換気」が定められ。
今回の住まい(第3種換気)では、機械換気のほか自然吸気が必要な訳です。その自然吸気の外壁側の
カバーがあまり見た目にも美しくないので写真のようなサッシを採用し代用とした訳です。
次はこんな写真
これも「換気」に関係すること。良く見たら屋根の際に「穴」が開いていると思います。
答えは言ってしまいましたがこれも換気口です。防虫ネットは張っていますよ。
因みにこの部分の事を「面戸」といいます。家の周囲にぐるりとあるので作るのが面倒くさいから「めんど」と
言ったとか言わないとか・・・・・・
次は
どこの事を指しているかといいますと、屋根垂木の際にある「溝」勿論これも大工さんが手で造っています。
今回の外壁の仕上は一部除いて「板」なので、それが差し込まれる部分です。
一般的に外壁に使われる「サイディング」にはこういった「役物」という名のパーツが沢山あり、それを使う
のですが、今回はすべて手造りのため作業する大工さんの経験と知識が必要で、こういった細かな部分
にも気を配らなければいけません。
他にも色々と細かい部分がありますが、また今度紹介の続きをしたいと思います。